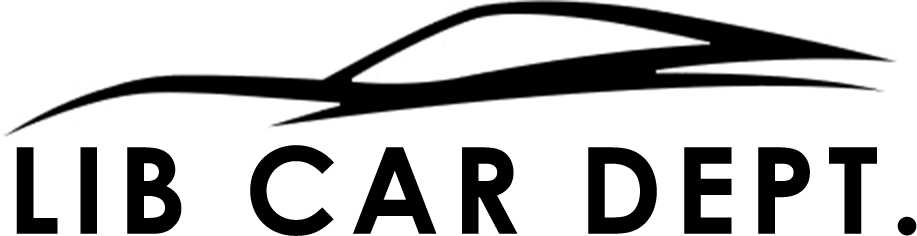中国発EV大手「BYD」が、日本市場から撤退するのでは? そんな不安の声が最近増えています。
検索トレンドでは「BYD 日本 撤退」「BYD 売れない」「BYD 買って大丈夫?」などのワードが急上昇。すでに車を購入した人はもちろん、これからEVを検討している人にとっても気になる問題です。
この記事では、BYD撤退の可能性・販売状況・安さの理由・故障率・今後の戦略まで、EV市場の変化を踏まえて網羅的に解説します。
画像引用元 : BYD公式サイト
BYD日本撤退の可能性はある?現状と技術トレンド
現時点での撤退の可能性は?
2025年現在、BYDから日本撤退に関する公式発表は出ていません。むしろ、全国100拠点展開や新モデルの投入計画など、成長路線が進められています。
ただし、EV市場の普及が進まない日本において、収益性の観点から将来的な撤退リスクがゼロとは言えません。補助金政策の変化や競争の激化が、撤退判断に影響する可能性もあります。
EV市場の特殊性と撤退リスク
日本ではEVの販売比率が1%未満と極めて低く、充電インフラの整備も地方では遅れています。BYDが得意とする「価格競争力」だけでは、日本の消費者の信頼を得るのは困難な状況です。

撤退したら何が起こる?オーナーが知るべき実情
修理・部品供給は続くのか?
日本の法制度では、メーカーが撤退してもリコール対応や補修部品の供給義務があり、一定期間のサポートは維持されます。
ただし、純正部品の入手が難しくなる、修理できる工場が限られる、工賃が割高になるといった実質的な不便は避けられません。
中古車価値への影響は?
撤退報道が出ると、リセールバリュー(下取り価格)は下がりやすくなります。購入を検討している人は、長期保有前提の選択か、数年で売却する前提の価格戦略を考慮すべきです。
日本でBYDが「売れない」と言われる理由
なぜ日本市場で苦戦しているのか?
2023年は約1,446台、2024年は2,223台と着実に販売台数を増やしているBYDですが、日本全体の自動車市場で見ればごくわずかなシェアです。
最大の理由は、日本がハイブリッド車(HV)優先文化であること。さらに、トヨタ・日産・ホンダなどの国内勢への信頼が圧倒的で、新興中国ブランドに対する警戒感も根強いです。
販売店・整備網の整備不足
日本全国をカバーする販売・修理ネットワークがまだ構築途中で、特に地方では購入後の安心感を得にくいのが現状です。
比較:日本EV市場における他メーカーとの違い
たとえばトヨタのbZ4Xや日産サクラは、販売後のサポート体制が整っており、販売店も全国展開されています。BYDはまだ数十店舗の段階で、安心感や信頼構築に課題を残しています。
それでもBYDを選ぶ人はいる?購入者の傾向と魅力
価格重視の新しもの好き層
BYDを購入する人の多くは、価格の割にスペックの高いEVに魅力を感じた人や、環境意識が高く最新のテクノロジーに興味を持つ層です。
「テスラは高すぎる」「日本のEVはデザインが地味」と感じていた層にとって、個性と価格のバランスが良いBYDは一つの解になります。
都市部の短距離ユーザーに支持
充電インフラが整っている都市部では、通勤や買い物などの短距離移動にBYD EVは最適。補助金を活用すれば購入ハードルも下がり、手頃な価格帯のEV入門車として一定の人気があります。
BYDはなぜ安い?その理由と裏側
垂直統合によるコストダウン
BYDは電池、モーター、インバーターなど主要EV部品をすべて自社で製造しており、部品調達コストを圧倒的に削減しています。
中国政府の支援+大量生産体制
中国国内での大規模生産と政府の補助政策が、グローバルでも価格競争力を維持できる背景です。
安い=悪い?装備や素材の違い
一部のモデルでは、内装素材や快適装備にコストをかけておらず、価格を抑えるために必要最低限にとどめている部分も見受けられます。そのため高級車に比べると“割り切り”が求められる側面もあります。
故障しやすい?品質への不安と実態
バッテリー性能は高評価
BYD独自の「ブレードバッテリー」は高い安全性と耐久性を誇り、発火リスクの低減が評価されています。
一方で不安視されるソフトウェア面
一部ユーザーからはインフォテインメント系の不具合やナビ精度への指摘もあり、まだ日本仕様への最適化が不十分という声もあります。
EV市場の将来とBYDの生存戦略
PHV導入やブランド認知向上に注力
EV一本では苦戦しているため、BYDは日本向けにPHV(プラグインハイブリッド)モデルの投入を予定。これにより地方部や充電環境が整っていない地域への対応力を高めています。
また、広告戦略として長澤まさみさんを起用したテレビCMなどを展開し、安心感と認知の向上を図るマーケティングも強化中です。
筆者の視点:もし筆者が今BYDを買うなら?
都市部でセカンドカー用途として短距離メインであれば「ATTO 3」や「ドルフィン」は魅力的。筆者自身はEVを所有した経験はありませんが、実際に車両を試乗してみると意外と乗り心地もよく試乗前より良い印象です。価格と性能のバランスは良いかもしれないですね。
ただし、10年乗り続けたい人や地方在住の方はサポート体制や再販価格を念入りに検討すべきと感じます。
よくある質問(FAQ)
Q. BYDのEVは壊れやすい?
→ バッテリー面は安全性が高いとされますが、ソフトウェア系や冬場の航続距離には課題あり。
Q. 撤退したら修理はできない?
→ 法律上一定のサポートは継続されます。が、部品供給が遅れたり価格が高騰する恐れあり。
Q. BYDとトヨタEV、どちらを選ぶべき?
→ 全国のアフター体制・長期信頼性を重視するならトヨタ。都市部で価格重視ならBYDもあり。
まとめ:BYDは「見切り」ではなく「見極め」が重要
- 現時点で日本撤退の公式情報はなし
- 2025年中に全国100拠点構築など攻勢戦略中
- ただし、普及率や信頼性、サービス網は課題
- 購入時はサポート体制と再販価格の確認を
「安いから」ではなく「自分の生活環境に合うかどうか」でBYDを選ぶことが、後悔しないEV購入のカギです。